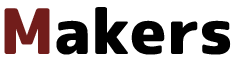【若者に選ばれる企業になる】”つながらない権利”について企業へ求められる対応を社労士が解説
2025.01.17

※この記事は、5分程度で読むことができます。
はじめに
「若い世代に選ばれる企業」として、これからの採用活動を成功させたいと考えている経営者や採用担当者の皆さまにとって、働きやすい環境づくりの象徴ともいえる「つながらない権利」は、注目すべきテーマと言えます。これは、労働者が勤務時間外に会社からの連絡や業務の指示を受けない権利を指します。
特に若い世代は、仕事とプライベートを明確に分け、ライフワークバランスを重視する傾向があります。この権利をしっかりと対応している企業は、採用の場面で有利に働くでしょう。
本コラムでは、企業がこの権利にどのように対応すべきか、具体例を交えつつ解説します。
1.”つながらない権利”の背景と意義
“つながらない権利”は、フランスで2017年に施行された労働法改正により法制化された概念として知られています。この権利は、以下の理由から注目されています。
・過労防止:労働時間が事実上延長されることを防ぎ、健康を守る。
・ワークライフバランスの実現:労働者のプライベート時間を確保する。
・魅力的な企業イメージ:特に若い世代から「働きやすい職場」として高い評価を得る。
日本においては法制化されていないものの、働き方改革や健康経営の文脈で多くの企業が取り組むべき課題とされています。
2.社会的現状と具体的な事例
“つながらない権利”が必要とされる背景には、労働環境の変化や社会的課題があります。以下に具体的な事例を挙げます。
1. テレワーク普及による境界の曖昧化
コロナ禍以降、テレワークが急速に普及しました。その結果、自宅が職場化することで勤務時間とプライベート時間の境界が曖昧になり、多くの労働者が「常に仕事に追われている」と感じる状況に陥っています。
具体例:東京都内のIT企業に勤務するAさんは、テレワーク導入後、深夜にも上司からのメールが届くことが増加。返信をしなければならないプレッシャーにより、精神的なストレスが蓄積し、最終的に適応障害と診断されました。
2. 海外企業の取り組み事例
フランスやドイツでは、”つながらない権利”を企業文化に取り入れる動きが進んでいます。
フランスの事例:大手IT企業では、勤務時間外のメール送信をシステム上でブロックする仕組みを導入。また、緊急時の連絡は専用ツールで記録することで、不要な連絡を最小限にしています。
ドイツの事例:自動車メーカーでは、勤務時間外に社員が仕事用の携帯電話を使用できなくするルールを制定し、これが従業員満足度向上につながりました。
3. 日本国内の取り組み
日本国内でも、一部の企業が「つながらない権利」を尊重する取り組みを始めています。
三菱ふそうトラック・バス株式会社:2014年12月から、長期休暇中の社内メールの受信拒否・自動削除が可能なシステムを全社員に導入しました。これにより、連休後に溜まったメール処理の負担を軽減し、業務効率化を図っています。
イグナイトアイ株式会社:業務時間外や土日祝などの休暇中は、仕事に関する電話やメールを禁止する方針を採用。取引先にも時間外対応ができない旨を事前に伝え、メールには自動返信で休暇中であることを通知する仕組みを整備しました。この取り組みにより、会社の売上が約4割増加する成果を上げています。
これらの事例は、若い世代の求職者が企業を選ぶ際の重要な基準にもなり得ます。
3.企業へ求められる対応
企業が”つながらない権利”を実現するためには、以下のような具体的な対応が求められます
1. 就業規則の見直し
労働時間外の連絡や業務指示に関する規定を明確に定める必要があります。
具体的には下記の様な内容です。
・勤務時間外のメール送信や電話連絡を原則禁止とする。
・緊急時の連絡基準を明確化する。
2. ITツールの使用ルール策定
メールやチャットツールの利用ルールを明確にすることも重要です。
具体的には、下記の様な内容です。
・メールの予約送信機能を活用し、送信時間を翌営業日に設定する。
・チャットツールの「通知オフ」機能を推奨する。
3. マネジメント層の意識改革
管理職が部下に対して勤務時間外に連絡を取る行為は、暗黙のプレッシャーとなる場合があります。これを防ぐために、管理職向けの研修や啓発活動を行い、働き方改革の意識を浸透させることが重要です。
4. 労働時間の適正管理
勤務時間が適切に記録される仕組みを整える必要があります。特にテレワークでは、労働時間が曖昧になりやすいため、勤怠管理ツールの活用が推奨されます。
5. 従業員への周知と啓発
“つながらない権利”の意義や具体的な取り組み内容について、従業員に十分な説明を行い、理解を深めてもらうことが重要です。
4.社会保険労務士ができる支援
社会保険労務士は、”つながらない権利”の実現に向けて以下のような支援を提供できます。
1. 就業規則の作成・改定
“つながらない権利”を明確にするための就業規則や規定の作成・改定を支援します。また、規定の作成にあたり、労働基準法や関連法令との整合性を確保します。
2. コンサルティング
企業の実情に応じた働き方改革のプランを策定し、実行を支援します。特に中小企業では、リソースが限られる中での現実的な対応策が求められるため、専門的なアドバイスが重要です。
3. 労働時間管理の仕組みづくり
労働時間を適正に管理するための仕組みづくりをサポートします。勤怠管理ツールの選定や導入支援、従業員への運用説明会の実施も可能です。
4. 教育・研修の実施
管理職や従業員向けに”つながらない権利”の意義や遵守方法を解説する研修を実施します。また、ハラスメント防止やメンタルヘルスケアに関連付けた内容での教育も提案できます。
5. 助成金の活用支援
働き方改革に関連する助成金の情報提供や申請手続きの代行を行います。例えば、「働き方改革推進支援助成金」を活用することで、企業の負担軽減を図ることが可能です。
まとめ
“つながらない権利”は、労働者の健康と生産性を守るだけでなく、企業にとっても持続可能な経営を実現するための重要な要素です。特に若い世代の求職者に選ばれる企業となるためには、この権利への対応が鍵となります。
社会保険労務士は、法令遵守や働き方改革の専門家として、企業の取り組みを強力にサポートできます。特に、中小企業においてはリソースが限られる中で、実効性のあるプランを提案する役割が期待されています。これを機に、企業と社会保険労務士が協力し、働きやすい環境の実現を目指しましょう。

福岡県・佐賀県で人事労務の課題解決のことなら、社会保険労務士法人メイカーズにお任せください!
新しい制度導入についてのご相談や具体的なアドバイスが必要な場合は、ぜひお気軽にお問い合わせください。中小企業の労務管理と人事制度の専門家として、貴社の課題解決をサポートいたします!